音楽レーベルSublime FrequencyのリサーチャーRobert Mills氏と、様々な音楽ユニットをはじめ多岐にわたる活動で知られるスタディストの岸野雄一氏をお迎えして、「耳の冒険家達へ -インド最古の録音から聞こえる音の世界-」についてお話を伺いました。会場は学内外から30名程度の参加者を迎え盛況となりました。当日の様子を本学大学院芸術工学専攻博士課程の松浦知也がお伝えします。
上映された1時間ほどの映像『This World is Unreal Like A Snake in A Rope』には台詞やナレーションは無く、字幕もほとんどありません。それはMills氏がインドをぐるりと渡り歩いた中でおよそ偶然巡り合った風景を撮り続け時系列もそのままに見せるものであり、ストーリーもドラマも無いにも関わらず、そこに溢れる街の雑踏、日常的に行われる宗教的な儀式や祭、道端で楽器を演奏する人たちの様子をただ聴いているだけで不思議と魅力的に感じられるものでした。
Millis氏はそうした、フィールド・レコーディング(その場所の音を録音する手法)を用いて音楽を作る傍ら、録音することのルーツに興味を持ち続けリサーチをしています。
19世紀の終わり頃、円盤に音を刻みつけるレコードが発明されてからすぐに、Frederick William Gaisbergという人物が世界中を巡って歌からコメディまで様々な音を録音し、これは歴史上最初期の市場に流通した録音物になりました。その中にはインドに加えて日本も含まれており、その調査がMills氏が今回来日している理由の一つでもあるそうです。
上映後、岸野氏によるレコードが音を録音し再生する仕組みの丁寧な解説を挟みながらMills氏がレコードの歴史を様々な側面から紹介し、Gaisbergらによる録音を紹介してくれました。
SP盤とも呼ばれる初期のレコードは、虫が木の表面に付ける樹脂を加工して作られるシェラックという素材でできています。インドはその虫の生息地域の一つだった故にシェラックの主要な生産国の一つであり、その意味ではレコードのルーツの1つとも言えます。シェラックは薬品や塗料など様々な用途に応用できるので、第2次対戦時に輸出が制限されるとシェラックを取り出すためにレコードを破砕して再抽出することが行われたり、それが後により容易に合成できる塩化ビニルが開発されLPレコードに用いられる契機ともなりました。
インドはシェラックの生産国であることもあってか、日本や欧米でSP盤の生産がされなくなった後も長くSP盤が生産・流通されました。そのおかげでインドや一部の国だけでビートルズのSP盤が作られマニアの間で超高額で取引されるようになったり、Millis氏はその偽物を掴まされたり、というエピソードも。一見社会と無縁に思える音楽もこのような形で複雑に結びついていることを学びました。
録音のルーツを知るということは、音という情報やそれを刻みつけるシェラックのようなメディウムが国や時間を超えて取引されることについて考えることでもあり、世界中を情報が駆け巡る現代に深い洞察をもたらしてくれるものでした。
参加者たちからの興味津々な質問に答えた後、最後にMills氏は15分ほどギターとフィールドレコーディング音を用いた即興演奏を披露してくれました。来場者が机の上に置かれたポータブル蓄音機の前で話し込んでいる傍ら、サウンドチェックとの境目無くいつからとも無く始まっていた演奏に、気がつけば全員が聞き込んでいる。その演奏は映像と同じく、明確に用意されたストーリーもドラマも無いけれど、その場で起きる出来事や偶然をポジティブに受け止め時間を少しづつ前に進めていく大変魅力的なものでした。
2019年より、九州大学大学院芸術工学研究院では、基礎論の枠に留まらないデザインの新たな可能性を探ることを目的とし、『デザインセミナーNEXT』を立ち上げ、実践的な活動を行うこととなりました。デザインの体系化を目的とするデザイン基礎学セミナーとの二本柱で、新たな教育方法の確立に取り組んでいきたいと考えております。
登壇者
Robert Millis
Sun City GirlsのAlan Bishopらと共にSublime Frequenciesを運営する米リサーチ界の最重要人物。SP盤の研究や収集が専門領域で、再発レーベルDUST-TO-DIGITALにも楽曲を提供している。ミュージシャンとしてClimax Golden Twinsの活動のほか、職業作家として多数の映像作品に提供しており、ソロでも活動している。映像作家としてタイの奇祭ピーターコン祭りの様子を収めた『PHI TA KHON: GHOSTS OF ISAN』、南インドの伝統行事を記録した『THIS WORLD IS UNREAL LIKE A SNAKE IN A ROPE』など数々のドキュメンタリー作品を制作している。フルブライト研究員として一年間インドに滞在し、SP盤の調査と記録を行いまとめた『INDIAN TALKING MACHINE』や民俗音楽学者Deben Bhattacharyaの足跡を辿り、膨大な音源を収録した『PARIS TO CALCUTTA: MEN AND MUSIC ON THE DESERT ROAD』などの著作も発表している。日本には1902~03年に行われた東アジアの最初期の商業レコーディングについて調査するために来日した。
岸野雄一 Yuuichi Kishino
1963年、東京都生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科、美学校等で教鞭をとる。「ヒゲの未亡人」「ワッツタワーズ」などの音楽ユニットをはじめとした多岐に渡る活動を包括する名称としてスタディスト(勉強家)を名乗る。銭湯やコンビニ、盆踊り会場でDJイベントを行うなど常に革新的な場を創出している。2015年、『正しい数の数え方』で第19回文化庁メディア芸術際エンターテインメント部門の大賞を受賞。2017年、さっぽろ雪まつり×札幌国際芸術祭2017「トット商店街」に芸術監督として参加。
日時
2019年6月19日(水)開場18:00 終演21:00
場所
九州大学大橋キャンパス音響特殊棟
福岡市南区塩原4-9-1
お問い合わせ
九州大学大学院芸術工学研究院 城一裕
jo(a)design.kyushu-u.ac.jp
Member
- Robert Millis
- 岸野雄一
- 城一裕 九州大学大学院芸術工学研究院
-
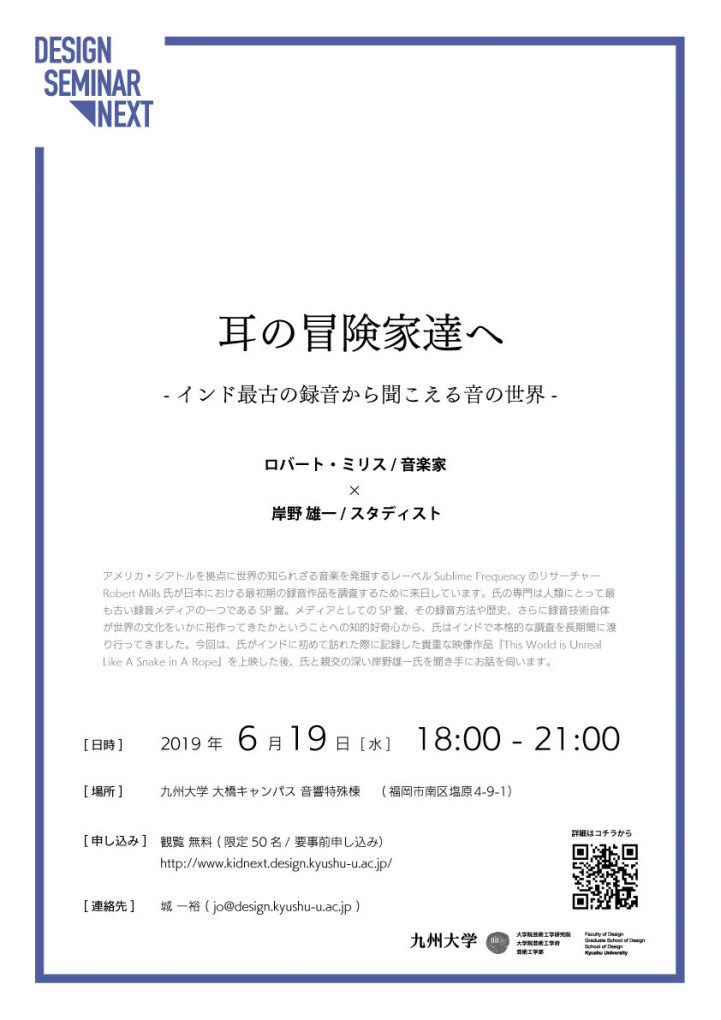 第1回デザインセミナーNEXTチラシ
閉じる
第1回デザインセミナーNEXTチラシ
閉じる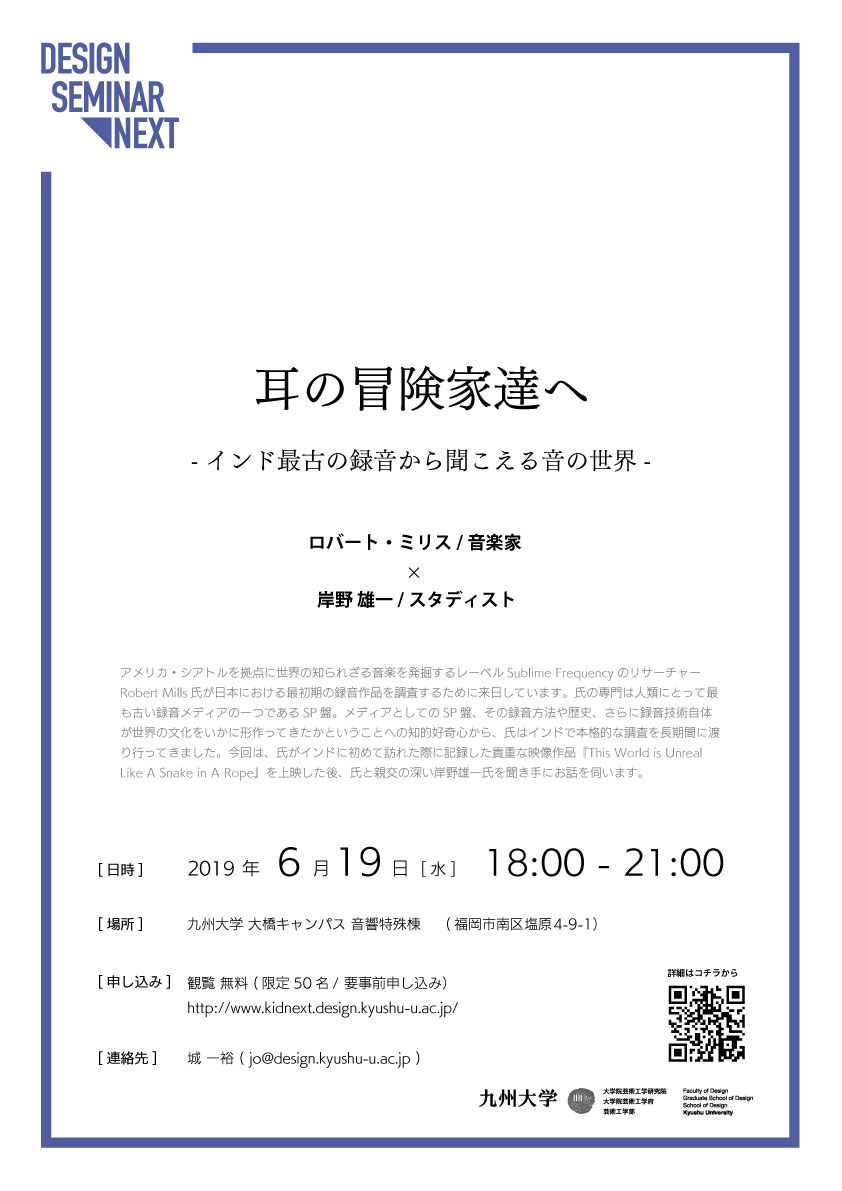
第1回デザインセミナーNEXTチラシ
![九州大学イノベーションデザインネクスト[KID NEXT]](https://www.kidnext.design.kyushu-u.ac.jp/wp-content/themes/kidnext/img/logo_header.png)










